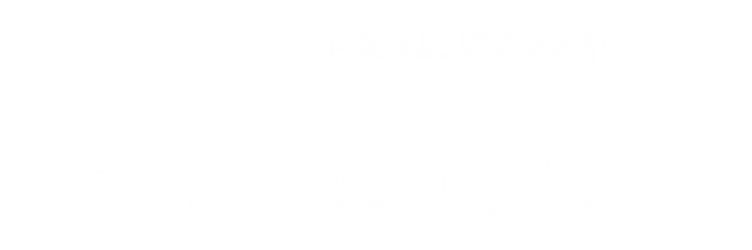毎年恒例となります氏子総代会の研修旅行に9月4・5日と行ってまいりました。
今年は巳年ということで、宮城県の金蛇水神社様へ正式参拝させていただきました。
由緒といたしましては、平安時代の半ば、小鍛冶宗近が、水神宮のほとりの清らかな川の水を使って一条天皇の御佩刀を鍛えることになりました。しかし、カエルの煩わしさのため、思うように作れなかったそうです。そこへ雌雄一対の蛇の姿を作れとの天啓を受けた宗近は言うとおりにしたところ、カエルたちはなりをひそめ、心を込めて宝刀を鍛えることができました。これに感謝し、雌雄一対の金蛇を水神宮へと奉納しました。このことから、この水神宮は金蛇を御神体と崇め、社名も金蛇水神社と称されるようになったそうです。(『金蛇水神社 参拝のしおり』より)
宮司様がいろいろなお話をしてくださり充実した実のある研修となりました。
お忙しい中にもかかわらず丁寧なご対応ありがとうございました。

続いて竹駒神社様を参拝させていただきました。
御本社も御末社も大変立派で落ち着いた境内の雰囲気に癒されました。

珍しい飛び跳ねている狐さんの像がありました。

参拝の後は、せっかくの機会ですので、気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館を見学しました。あらためて津波の恐ろしさとともに、現地の皆様のご苦労を思い知る機会となりました。
また、曇天ではありましたが、松島をフェリーで観光し、絶景を堪能することができました。
豊富な知識をおもちのガイドさんからたくさんのためになるお話や楽しいお話を聞きながらの旅行でしたが、2つだけここに載せさせていただきたいと思います。
♦ 「松島や松島やああ松島や」という句は、松尾芭蕉が作ったものと思われてい る方が多いと思いますが、松尾芭蕉は松島のあまりの美しさに句にすることができなかったようです。
それを知った田原坊が美しい松島を句に表せないことを「松島や松島や、ああ松島や」と表現して、桜田周甫の記した『松島図誌』という現代でいうと旅行ガイドブックのようなものに、キャッチコピーとして載せたものが、松尾芭蕉の句として誤って広まったそうです。
♦ 独眼竜政宗は眼帯をしているというイメージを持っている方も多いと思いますが、実際は、眼帯をしている肖像画や銅像はなかったそうです。両目を健康に生んでくれたにもかかわらず、病で片目の視力を失ってしまったことを親に申し訳ないと思う気持ちから、肖像画も銅像も両目をきちんと描くよう遺言したとのことです。
しかし、映画や大河ドラマで独眼竜政宗役が眼帯をしたことから、眼帯をしているイメージが世間に広まったそうです。
お陰様でバスの中も見学場所もとても楽しいひと時を過ごすことができました。
来年も良い研修にしたいと思います。